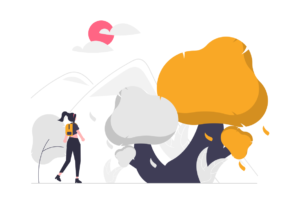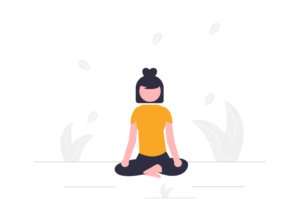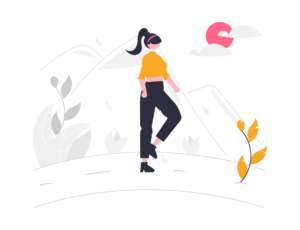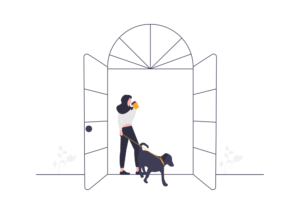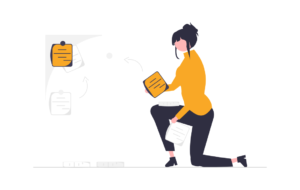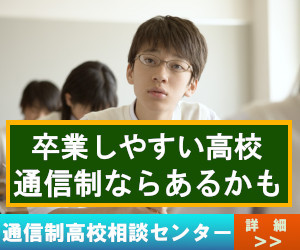コロナがもたらしたもの

変化と向き合う
「天災は忘れた頃にやってくる」で有名な地球科学者の寺田寅彦は次のように述べています。
日本列島は「慈母」と「厳父」の2つの顔を持つ。そこに暮らしてきた日本人は、「厳父の厳訓に服することは慈母の慈愛に甘えるのと同等にわれわれの生活の安寧を保証するために必要なこと」だと認識していた。
ひとたび「厳父の厳訓」を受けるとそれまでの日常は破壊され、多くの命が失われてしまいます。災害と戦争が続いた中世日本では、世の中に不変のものはないという考え(諸行無常)が広まりました。
無常観と聞くと悲壮感が漂いますが、徒然草に「世は定めなきこそいみじけれ」とあるように、移ろいゆく儚きものを美意識へと昇華させたのが吉田兼好です。これは日本文化の美的感覚(幽玄)へと引き継がれていきました。
コロナがもたらしたもの
あらゆる枠組み・価値観を捉え直す局面に来ました。これまでのやり方が通用しない、誰もが経験したことのない事態に陥っています。
発生源は諸説ありますが、主に中国武漢から世界中に広まった新型コロナウイルスがもたらした影響は極めて大きいです。ウイルス核は0.1µm(1mmの1万分の1)と極めて小さく、発症後の治療法も確立されていません。
世界有数の災害大国と言われ、同時に防災意識が高く評価されている日本でも混乱は大きいです。即時的な物理破壊を伴う地震や台風と違って、感染から発症まで時間差があり、感染力を有する無症状者も存在することから被害状況の把握が困難です。全世界レベルで広まり、被害のピークがいつなのかも不明瞭です。
全国の学校は休校に追い込まれました。私の大学も封鎖され、実験の継続ができなくなりました。一人ひとりが考えるべき時期です。生活が一変した現在、あなたはどのような社会を創造したいと考えていますか。
オンライン授業
大学のTA(講義補佐)を務めています。東大の講義は全てWeb会議ツールであるZoomが用いられるようになりました。Zoomは画期的なサービスで、先生の映像を見ながら、チャット(メッセージ)で質問ができます。さらに、生徒のPC画面も参加者全員で閲覧することが可能なため、疑問点はすぐに共有できます。以前よりも全員参加・双方向型の傾向が高まったと感じます。単なるオンデマンド配信(映像を配布していつでも見られる一方向の形式)とは違って、リアルタイムだからこそ実現できたことは多いです。
ただ、長所だけではありません。デメリットも数え上げればキリがないです。
真っ先に思い浮かぶのが教育格差の助長です。生徒の通信機器やスキルによっては講義を十分に受けることができません。ネットやPCに慣れている人は問題ありませんが、不慣れな人は機能を十分に使いこなすことができません。自宅で授業を受けられる環境を整えられないケースも多いでしょう。
また、教室という空間が持つ機能も失われます。友人たちと話したり、先生が紹介してくれる本・資料を手にとったり、試料に触れたりといったことができません。当然ながら机の感触や床がきしむ音、教室特有の匂いも失われます。すべては画面越しでのやりとりです。
最後に、体験学習が不可能な点です。例えば、図工や音楽と言った授業、理科の実験、社会学習はオンラインでは成り立ちません。同級生と一緒に作品を作ったり、みんなでリズムを合わせて歌ったり、実験器具を取り扱ったり、実際に働いている人の姿を見て話を聞いたりといった「本物の体験」ができません。学校の主な役割は机上の勉強ではなく、コミュニティ形成と共同作業の機会を提供することだと考えますが、これらの機能が失活してしまえば、学校の存在意義も崩れてしまいます。
自宅学習をスムーズに進めるコツ
休校が続く中、最も必要とされる力が自学自習力です。自分で勉強を続けられる子どもとそうでない子どもでは日が経つごとに差が開いてしまいます。
紙幅が残り少ないため手短にまとめますが、以下の手順を意識すると自宅学習がスムーズに進みます。
- その日にやることを決める
- 家庭用時間割をつくる
- 勉強中は勉強だけに集中
これには規則正しい生活習慣が大前提になってきます。決まったルーティンを組むことでリズム良く学習することができます。過去の記事も参考にされてください。